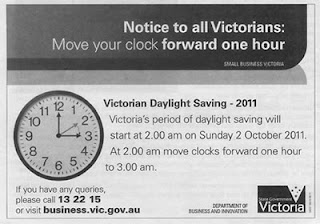「うそぉ!死んじゃったの?」と思わず叫んだ。
AppleのCEO職から退いたのは、ほんの数週間前のことだ。
こんなに早く…。
まだ、56歳だったのに。
長年、彼の健康問題がメディアはもとよりMacファンや多くの人の関心事だった。肝臓の手術をしたのは知っていたし、Apple新商品のプレゼンテーションに登場する度に目に見えて痩せていたので、深刻な病気を抱えていることは知っていたけれども、膵臓がんと戦っていたことは、今朝新聞を読むまで私は知らなかった。
初めてMacのコンピューターを見たのは、1988年のことだ。私は、アメリカのアラバマ州、レッドベイという街の学校で日本語や日本文化を教えていた。その学校は、キンダーから12年生まである学校で、レッドベイの街は小さな田舎町だったが近隣の地域からスクールバスで子供達が通ってくるので、生徒は1000人以上いたと思う。その学校の小学部の図書室内のオフィスを、私は準備室として使っていた。
その図書室に小さな四角いちょっと黄色っぽいベージュ色のコンピューターがあった。かじったリンゴの絵がついていて、Appleと書かれていた。変わった名前だなと思ったのが最初の印象だ。そのコンピューターは、各教室で良い行いをしたり学習や学校活動で顕著な努力を認められたりした生徒がご褒美として使用を許されているクイズマシンのようなものだった。
 |
| アラバマの小学校で見たMacintosh 128K |
生徒は、フッロピーディスクを挿入し、次々にスクリーンに表示されるクイズを読んで、マウスを使って答えを選択したり、キーボードで答えを入力して行く。文字だけでなく、画像も表示されていた。そのようなコンピューターを見るのは初めてだった。 当時、私は東芝のワードプロセッサを愛用していたが、その四角いコンピューターはワープロとはレベルが違った。慣れた手つきでその四角いコンピューターを使う子供達を見て、アメリカという国はなんと進んでいるのだろうかと心底感心したものだ。
その後、自分用のパーソナルコンピューターを購入しようと思った頃には、ウインドウズの時代となっていて、 Macよりもウインドウズと多くの人に勧められて四角いベージュ色のPCを買った。それで満足していたのだ、iMacを見るまでは!
私が初めて見たiMacは、オレンジ色のマシン。でっかい箱型のコンピューター本体が横に置いてないので、(っ?)と思ったのを覚えている。小さいおしゃれなテレビみたいなそれが、ディスプレイ&コンピューター一体型のマシンだと知った。私が使っていたベージュ色のでっかい箱&ベージュ色のでっかいディスプレイと比べたら、それはもう異次元の製品。スタイリッシュなデザイン。場所を取らないコンパクトさ。とにかくカッコイイと思って見とれた!
 |
| オレンジ色のiMacとの出会いは衝撃的だった |
iPodは、使っていたがそれなしで生活に不便を感じるようなものではなかった。しかし、iPhoneは必需品となっている。現在の私には、iPhoneの無い生活は考えられない。一度、iPhoneのマイクが故障して音を拾わなくなり修理に出した。郵便局に故障した iPhone を預けて、修理が終わって戻ってくるまで1週間。(保証でカバーされて1ドルも費用はかからなかった。)その1週間、本当に不便だったし、なんだか不安だった。そして、最近では、iPhoneの画面が小さすぎて、眼鏡無しでは文字を読むことが困難になって来たので、iPadが欲しくなっている。
ちょっと何か調べものをしたい時に、いつでも情報が得られる手軽さ。知らない場所へも迷わずたどり着けるナビゲーションや地図機能。電車の発着時刻や乗り換え情報もすぐ調べられる。家族や友達と遠く離れていてもつながっていられるソーシャルネットワーク。いつでもメールをチェックして、スピーディーな情報交換。レシピ探しもチョチョッと簡単に見つけられる。テレビの前ではテレビガイド。退屈な待ち時間には音楽を聴いたりビデオを見たりゲームをしたり。携帯電話にメーッセージを送信。信じがたいテレビ電話機能。写真やビデオをいつでも撮影。ああ、とても書ききれない。こうした日々日常的に使っている機能の全てがこの小さなiPhone一つに入っている。
スティーブ・ジョブズは、確かに世界を変えた。初めてあの四角いMacを見て衝撃を受けた1988年からわずか20年ほどの間に、どれほど私たちの生活が変わったことか。世界が変わったことか。彼が健康でこれからさらに20年生きていたら、その間にどんな変化が起きただろうか。第2のスティーブ.ジョブズが現れて、世界はさらに変わって行くのだろうか。
今日は、様々なウェブサイトでスティーブ.ジョブズの名言(Quotes)を読んだ。一番好きだったものをここに紹介します。
「Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. 」1987
私も、自分の心に従って生きたい。
お帰りの前に1クリックを!